かみじょー作小説
小説を書くにあたって、大切なことはとにかく書いてみること。
下手でもなんでもまずは書いてみないと始まらない。
それ以上に大切なことは自分が創りだした世界を信じること。
どうせ、フィクションだろ!って覚めた気持ちだと臨場感のある作品は書けない。
それはただの文字の羅列になってしまうから。
文章を書く。
記事を書く。
食事をする。
すべて自分が生きた証、足あとを残す行為。
そこに高位も低位もない。
他人と比べなくても大丈夫!
だって生きるって自分の人生を!だから。
人の人生を生きているわけでないってことを人は忘れがち。
つまりは、自分には自分固有の世界を持っていて、
そして、その世界はタイムリミットが残されている。
だから懸命に生きねば!
足あとを残さねば!と僕は思うのだった。
痛みキャンディ第五話公開
許すこと。
それがおれにはできなかった。
記憶から消し去り、「なかったこと」として押し込めた過去。
怖くて怖くて、もう触れられない過去。
それでも本当は触れないといけない過去。
触れてみないと、許してあげないと、おれは先にはすすめないとわかっていた。
わかっていてずっと逃げてきた過去。
そして
戻りたい、やり直せたらと思わせるいつかの昨日。
ギュッと抱きしめてすべてを許されたいと望む昨日。
最近朝目が覚めると涙を流していることがある。
怖い夢を見たわけでもない。
悲しいわけでもない。
涙はどこから流れてくるんだろう。
泣いたって世界は変わらないのに。
それでも人は時折涙を流さずに入られない。
僕がずっと置き忘れてきた涙が堰を切ったように流れてきた。
何か戻らないものが夢の中に出てきておれを呼んでいる。
それがなんなのか。
大切な部分はぼやけてしまいわからない。
失ったことすら気が付かないように少しずつ自分の足あとは靄のかかった何かに覆われていく。
鮮明だったはずの忘れたくない景色も
誰かの笑顔も、時と一緒にすべてがぼんやりして見えなくなる。
あの懐かしい声は誰なのか。
おれは感情を忘れた。
いや、忘れていたと思い込んでいた。
そう思いたかった。
少しずつそれが思い出されてきた。
それは過去を受け入れること。
おれにとって最も恐ろしいこと。
病気も治りかけの朝。
クゥはいつものように、おれの枕元で跳ね回る。
おれの大切な家族。
たった一人の友人。
体調が悪かったので買い物も行けずクゥの食べるものもそろそろ底をついてしまう。
おれはスーパーへと出かけた。
歩いて10分。
いつもの道を何気なく歩く。
十字路の脇でシャベルカーが家を取り壊していた。
静かな空間を壊すような濁音混じりのあの音は、
まるでおれの世界の一部が誰かの手で破壊されているかのような焦燥感。
街の景色は少しずつ変わっていく。
誰も気が付かないうちに。誰にも気にも留められることなく。
ずいぶん商店街も変わってきた。
あそこにあった魚屋も今は威圧的な高層マンションに変わっていた。
その影が街を侵食していくようで気持ち悪かった。
変わらないものなんて何もない。
スーパーで必要な生活用品を買いそろえて帰宅する。
出来るかぎりスーパーなどに長居はしたくない。
家族を連想させるあの場所はいつまでも居心地がわるい。
おれが持てなかった笑顔や団欒、家族ってやつを見せつけられているようで、
そんなものも築けないお前は落伍者だと言われているようで…
そそくさと用を済ませては足早に去ってしまいたい。
何を買ったのかも朧なまま僕はレジに並んだ。
クゥのミルクは買ったし、おれはレトルト食品で十分だ。
会計を済ませて袋に詰める。
単純な作業。
全部簡単に何かに詰め込んでなかったことにできたらどんなに楽だろう。
なんてことを考えながら、白いビニル袋が膨らんでいく。
少し重い買い物袋を提げてさっきの道を歩いていた。
シャベルカーの作業は終わったみたいだ。
昨日まで在ったはずの家はもう見る影もない。
この光景は「死」と似ているな。
なんとなくおれはそう思った。
昨日まで生きていた人が今日はもういない。
そこにあったモノがもうない。
会話ができない。
でも時間は巡る。
人は歩きを止めない。
季節は変わる。
心臓の鼓動が聞こえた。
そう変わらないものなんて何もないから。
その解体された跡地に中年の男性が哀しそうな瞳をしながらその跡地を眺めていた。
おれも足を止めそっと眺めてみた。
「ここに思い出が沢山あったんですよ。」
中年の男性は話し掛けてきた。
「はぁ。そうなんですか…」
そっけなく受け応える。
「それがなにもかも壊されちゃってねぇ。」
と切なそうに俯く。
瞳には涙がこぼれそうなくらい溜まっていた。
あと二粒。
コーラの味と淡い炭酸が弾けた。
何かが自分の中に広がってきた。
それは
封印したはずの遠き日の思い出。
黒ずんだ過去。
おれはただ泣いていた。
飼っていた犬が死んでしまったから。
お墓を作ってあげた。
あっけない死への哀しみよりも言葉にならないような孤独感と切なさでいっぱいだった。
一緒に散歩した。
頭を撫でながら寝かしつけた。
一緒に家出もした。
そんな思い出が弾けてしまうのが怖かった。
そんな思い出が思い出になってしまうことに恐れた。
死そのものを受け入れず、その痛みからも逃げていた。
全ては変わる。
別れは必ずやってくる。
クゥを飼おうと思った時もそのためらいがなかなか払拭できなかった。
視線を戻すとおじさんはおれの肩を軽く叩きながらこう言った。
「それでもね、胸ん中にたくさんあるんですよ。
うれしかったことも、悲しかったことも。
愛しい全てが。
だから全てなくなったんじゃないんです。」
と優しく諭すように。
それはおれが泣いていたからだろう。
突然泣きだした知らない男に対して、痛みを知る者の手は優しかった。
その手はとても温かかった。
「ありがとうございます。」
おれは照れ臭さを隠そうと慌てた。
おじきしてから走って帰った。
「思い出」は形を変えて生き続ける。
おれにもある「あの思い出」もきっとまだ生き続けているのだろう。
涙を拭いておれはクゥの待つアパートへと向かって走った。
家に着くとさっそくクゥにミルクをあげた。
その時。
ジリリリ……
ジリリリ……
電話が鳴りだした。
それはあの人からの10年ぶりの電話だった。
writer:かみじょー
痛みキャンディ続きはこちら
・痛みキャンディー第二話
・痛みキャンディ第三話
・痛みキャンディ第四話
・痛みキャンディ第五話
・痛みキャンディ第六話
・痛みキャンディ第七話
・痛みキャンディ第八話
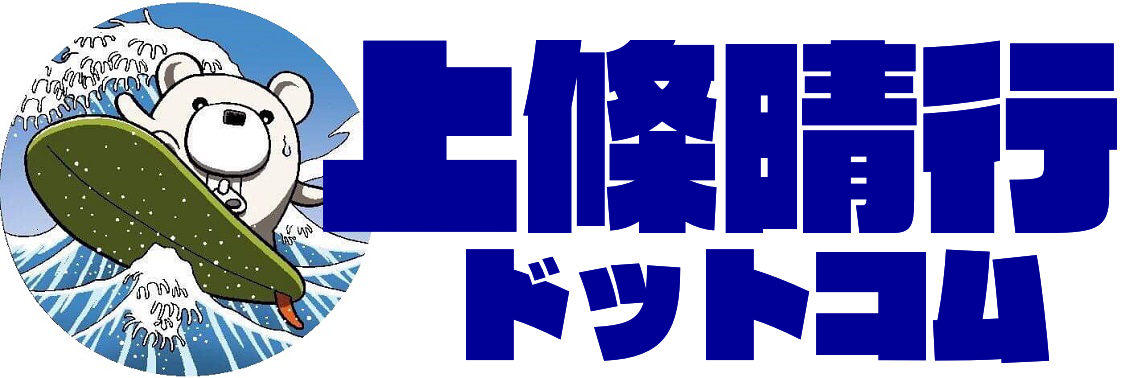


コメント